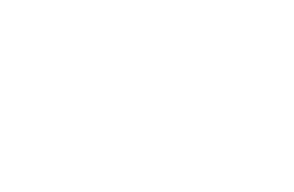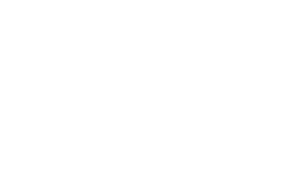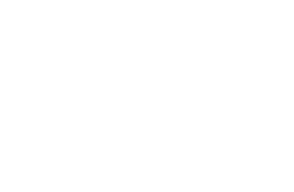第5章 コロナ禍での苦境と前進
Vol.5
コロナ禍での苦境と前進
2019年1月に法人化し、手探りでリスタートを切った413。スタッフの採用、部屋のメンテナンス、庭の整備、サイトの改修──まるでゼロから宿を立ち上げるような日々を重ねていった。少しずつ宿泊者が増え、SNSや口コミでも存在が知られるようになり、「ここからだ」とようやく手応えを感じ始めた矢先だった。
リスタートから1年。2020年、世界はコロナウイルスという未曾有の危機に直面する。旅行どころか外出すら制限され、沖縄への観光客は激減。413も例外ではなく、営業はままならず、客足は一気に途絶えた。私たちは、まるで光のないトンネルに放り込まれたようだった。
毎日のようにニュースで流れる感染者数。マスク、消毒、ソーシャルディスタンス──生活の常識が一変する中で、スタッフを抱える施設は「閉める」選択肢を取ることもできない。朝起きては蔓延する数字を確認し、ため息をつく。そんな日々が続いた。

それでも立ち止まるわけにはいかなかった。「仕方ない、できることを探そう」。そう自分たちに言い聞かせ、お部屋の清掃、カフェの合理化、ガーデンの手入れに励んだ。人が訪れなくても、施設を整えることで未来への準備を積み重ねていった。
やがて、その流れは工夫と挑戦へと広がっていく。「カフェのカウンターの高さをもっと使いやすく調整しよう」「収納式のDJブースを作れば、空間をイベントでも日常でも柔軟に活用できる」。そうした小さな工事や制作にも着手した。大変な状況だからこそ、自分たちの手で空間を進化させていこうという想いが強くなっていった。


さらに新しい発想も芽生えた。「カフェにサインを描いてもらおう。もっと存在を知ってもらえるように」「アパレルグッズを作ろう。413を旅の記憶に残せるように」「部屋の滞在体験をもっと豊かにしよう」。
ガイドブックに載らない「大人の隠れ家」として売ってきた413。けれど、閉ざすだけでは未来は開けない。むしろ「もっと外へ開いていこう」と発想を転換し、再開に向けて準備を重ねていった。

その過程で大きな力になったのは父の存在だった。梅雨のある日、二人でガーデンにデッキを作った。設計図は父の頭の中だけ。2日ほどで仕上がると、父は笑いながら言った。「もう2つ作ろうか」。結局その週のうちに3つのウッドデッキが並び、サンセットを眺めながらのオリオンビールは、心と体に達成感を運んでくれた。


小雨の夕方、父がふと斜面を見上げて言った。「この土地、もったいないな。少し危ないし……ここにも長いデッキを作ったらどうだ?」。翌日にはもう材木が届き、また二人で基礎から組み上げた。ほんの1週間で完成した長いデッキは、ガーデンをより広く、開放的な空間へと変えてくれた。


お客様はゼロ。カフェに来る人もわずか。それでも、自分たちで手を動かし、形にしていくことで「やれば道は開ける」という父の背中を見て学ぶことができた。

確かにコロナ禍は厳しかった。だが、この静寂の時間で積み重ねた工夫や努力は、後の413にとって大切な礎になった。
「お客さんがいなくても、やることはある。やれることをやれば、必ず次につながる」。そう信じる気持ちを失わなかったからこそ、私たちは止まらずにいられた。